En tu ausencia いない間に
スペイン映画 (2008)
思春期を迎えた13歳の少年パブロが、亡き父の戦友と出会ったことで生じる様々な想いを、アンダルシアの美しい田舎の風景のなかで描いた抒情詩。パブロは、大好きだった厳しい父を、自らの不注意で死なせてしまったトラウマから抜けきらずに思春期を迎えていた。母と2人で、村からかなり離れた一軒家に住んでいる。ある日、パブロの愛犬が田舎道で車とぶつかりそうになり、パブロはパコと運命的な出会いをする。その直後、村で唯一人の郵便配達がその場で2人に出会うが、これも運命的。パブロが、パコに対して親しみだけでなく一種の愛情まで抱くようになるのに対し、郵便配達は最初からパコを胡散臭い余所者として扱い、各所で噂話を拾い集めては、パコを悪者に仕立て上げていく。パブロが、友人の息子だと知った後のパコは、特に、友人が亡くなったと知らされると、パブロを忘れ形見のように可愛がり、一種の催眠術でトラウマも軽くしてくれ、パブロもパコを心から慕うようになる。そして、パブロの中に潜んでいた「子供らしいホモ」的な発想から、パブロの前で自分の体を捧げることで感謝の気持ちを現そうとする。しかし、パコは相手にしないどころか、村を出る時が来たと言い出す。それは、郵便配達のせいで、パコが2年間刑務所にいた前科者であることが知れ渡ってしまったから。パブロは必死で止めるが、パコは数時間後に村の広場で会おうと言って別れる。しかし、偶然家に戻ったパブロが見たものは、パブロの繊細な心をバラバラにするようなものだった。題名の「いない間に」は、直接的には、この最後に、パブロがいない間に、かねてから好きだったパブロの母とパコが愛し合う行為をさしている。しかし、それ以外にも、パコの悪い噂が、彼が宿にいない間に宿の女将から村中に広まったり、パブロがいない間に湖に泳ぎにきた子が事故死し、罪がパブロになすり付けられたりするなど、「いない間」の事態の変化が映画のキーポイントになっている。
13歳のパブロは、スペイン南部の片田舎の一軒家で、母と2人だけで暮らしている。近くに住んでいるのは、認知症の祖父と2人で暮らしている2つ年上の少女フリアだけ。母は、生まれた時からここに住んでいる訳ではなく、父と結婚した時か、パブロが結婚した時か、あるいはもう少し後になって、この家に引っ越してきた「余所者」だ。一方のフリアは地元育ち。辺りには子供は2人しかいないので、2人はじゃれ合って大きくなってきた。その平和な暮らしに、ある日、パコという男が入ってくる。最初は、パブロの愛犬を轢きそうになった車のドライバーとしてだった。その車はエンジントラブルで動かなくなってしまい、親切なパブロは村のガレージに連れて行ったり、修理に数日かかるとかで、村で唯一宿泊が可能なバルに案内したりする。その際、パブロの父がパコの親友だったことが分かり、パブロはただの案内人から、親友の息子に昇格する。そして、パブロは、父と会いたいといったパコを、父の墓に連れていく。これで、パブロは、亡き親友の忘れ形見となる。しかし、パブロには隠しておきたい過ちがあった。パブロの「うっかり」のため、父を死なせてしまった暗い思い出だ。パコは、パブロのどこか寂しげな様子の中に、何か悩みを抱えているに違いないと思い、丘の上に連れて行き、横にならせて心を解放させる。これで、ある程度、自分が許せるようになったパブロは、亡き父の親友ということも加わり、パコのことが大好きになる。一方、この小さくて閉鎖的な村には、詮索好きで、噂話をばらまくことしか能のない郵便屋と、パコの過去を偶然知っていて、それを言いふらすバルの女将がいた。お陰で、パコがかつて刑務所にいたことや、ヘレスという町でパブロの母と仲が良かったことまで知れわたってしまう。パブロがフリアに袖にされ、パコを辛い思い出のある湖に連れて行った時、悲劇が起きる。後から湖に泳ぎにきた少年が投げた石が、もう1人の少年に当たって死んでしまい、その少年は、自分の罪をパコになすりつけたのだ。お陰で、パコは村人に追われる身となる。村にいづらくなったと感じたパコは、村を出て行く前に、昔から好きだったパブロの母と愛し合っていたところをパブロに見つかる。そして、自暴自棄になって家から出た飛び出したパブロを追って、半裸で外に出たところを、「水死少年の犯行者」だとして追って来た郵便屋に見つかり、銃で撃たれて大ケガを負ってしまう。パブロにとっては、父の親友は姦通男、母は「恥知らずのふしだら女」になってしまい、救いのない立場になってしまう。
パブロを熱演するゴンサロ・サンチェス・サラス(Gonzalo Sánchez Salas)は、映画出演はこれ1作のみ。1996年1月1日生まれと何にでも書いてあるが、あまりにきりがいいので本当だろうか? 映画の最初の上映は2008年10月7日。夏のシーンがあるが、2008年の夏撮影していたのでは、とても映画はできない。2007年夏の撮影とすれば、撮影時11歳となる。映画の設定の13歳とあまりに違い過ぎるし、顔、体つきとも11歳には見えない。ゴンサロは、堂々たる主役なので、画面に出ずっぱりだが、この映画にはもう1人、脇役としてルイス・バルガス・ゴメス(Luis Vargas Gómez)が出演している。こちらも、映画出演はこれ1作のみ。生年は不詳だが、こちらはちょうど11歳くらい。ガレージ屋の息子で、出番は少ないが重要なパート。
あらすじ
一人の中年の男性が、暗い部屋で、車椅子に座ったまま話している。「パブロ、私は ずっと君のことを考えてきた。信じないだろうが、話すべきことは山ほどある。あの時、君は幾つだった? 11か?」。窓際に立ったまま、外をじっと見ている若者が、「13」とだけ訂正する。「あの時、起きたことは… 起きてしまったことは… 私に不満を言う権利はない、そう思ってるんだろ?」。ここで暗転。いきなり、鮮やかなアンダルシアの野原が映り、オープニング・クレジットが表示される。パブロが、地面に腹這いになり、地面に生えているキノコを生のまま食べている。そして、光溢れる野原を走る。どこまでも。途中で立ち止まって思わず吐いてしまうのは、キノコのせいなのか? パブロは、アンダルシアに特に多い「オズボーンの雄牛」の巨大看板(全長14m)の下を走り、崖っぷちに立つとオナニーを始める(1枚目の写真)。パブロは思春期に入ったところだ。最後は、自宅に戻る。白い壁と淡い茶色の屋根瓦が如何にもアンダルシアらしいを一軒家だ(1枚目の写真)。パブロは、定番のオレンジのシャツを脱ぎ、真っ白なシャツに替えようとするが、母は、新品だからと止めさせる。パブロは結局シャツを着ないまま食卓につく。そして、何も食べようとしない。「お食べ」。「お腹空いてない。もう食べた」。「そう? どこで?」。「野原で」。「野原で?」(3枚目の写真)。「キノコさ」。そこで、母は牛乳を飲ませようとするが、パブロは一口飲んで止める。「今朝、ここにいた人、誰なの?」。「お前に関係ないでしょ。いちいち干渉しないで。母さんは大人なんだから、自分の事は自分でできる」。誰と訊いただけなのに、ひどい過剰反応だ。その上、亡き父の銃を勝手に持ち出したと叱る〔射撃練習に銃を持ち出すパブロの癖は伏線〕。この母親、優しくない上に、顔もくたびれていて、魅力はほとんどゼロに近い。



そこに、近くに住んでいるフリアが勝手に入ってくる(1枚目の写真)。この辺りに住んでいるのは彼女の一家だけなので、出入り自由なのだ。パブロにとっては2つ年上だが、いい遊び相手。彼女は両親を亡くし、今は、認知症で土でも食べる祖父と一緒に暮らしている。本来ならば、孤児として扱われてもいいような状態だが、人里離れているせいもあり、ずるずると状態を引きずっている。フリアは、思春期の真っ只中で、言葉は悪いが発情期。だから、年下でも、パブロに構いたくて仕方がない。今日も、野原にあった花をパブロの髪に挿して戯れる(2枚目の写真、矢印は花)。フリアは、「散歩に行く?」とパブロを誘う。パブロはいつものオレンジ色のシャツを着て一緒に出かける。パブロは、さっそく、ソーシャル・サービスのことを訊いてみる。フリア:「あのクソッタレども。あたいを連れてくつもりなんよ。アホ連中め」。「ホントに連れてかれるの?」。「郵便屋が、助けてくれそうなダチを知ってるって言ってたから、来ないんじゃないかな」〔伏線〕「けど、あたいでも何とかできそう。もし、クソ女が来たら、こうしてやる」とパブロの股間を蹴る真似をし、「マンコを蹴り上げ、3年は生理がこないようにしてやる」。「男だったら?」。フリアはパブロの腰をつかむと、「顔におっぱいを押し付け、来たトコまで引きずって行ってやる」と、実践してみせる(3枚目の写真)。パブロは、フリアにとって いいオモチャだ。



パブロが、野原で愛犬と仲良く遊んでいると(1枚目の写真)、野道を小型車がやって来て、犬が急に走り出す。車が急停止したので、犬が轢かれたのではないかと心配してパブロが駆けつけると、犬は、車から降りた男〔パコ〕に抱かれていた(2枚目の写真)。パコは、パブロが友人の息子だとは知らないので、ひどく素っ気ない。犬をなかなか返さなかったりと意地悪なところを見せる。最後には、犬を返し、車に乗って出かけようとするが、エンジンがかからない。ボンネットを開け、パブロにキーを回してもらい、エンジンの調子を見るが、自分では直せないとあきらめる。パコは、路傍のコンクリート台に座ると、パブロに、「こんなトコで一生を送るつもりか? ちょっとこっちにおいで」と横に座らせる(3枚目の写真)。心優しいパブロは、「きっと 何とかなるよ」と慰める。「そうか? どうして?」。「父さんは言ってた。車は人間みたいなもんだって。息をしてる間は、まだ生きてる」。「父さんは車に詳しいのか?」。この後の2人の話の中で、さっきの犬は2匹目の愛犬だと分かる。野原にいたのをパブロが拾ってきて、父は、犬の行動に対して全責任を持つことを条件に飼うことを許す〔1匹目の顛末については、後で出てくる〕。この話が終わる頃、郵便配達の男が自転車でやってきて、「こっちへ来るのが見えた。村に行くのかね?」と尋ねる。「通り抜けるだけだ」。「遠くから来たのかね?」。「ああ。ずっと北から」。「サンタンデール、サンセバスチャン〔ともに、スペイン最北端の都市〕?」。「そっちの方だ」。「村に行くのかね?」。「通り抜けるだけだ」。この男、実に詮索好きだ〔後で、最悪の人間だと分かる〕。話は、ようやく車が動かなくなったことに到達する。郵便屋は自分でエンジンをかけてみて、オーバーヒートだと勝手に決めつけ、北のどこから来たのか さらにくどくど訊いた後で、ようやく去って行く〔助けを呼ぼうとか、どこに行けば修理してくれるとか、重要なことは何も口にしない〕。



ところが、郵便屋は少し離れると、自転車を止め、封筒を振って「パブロ、手紙が来てるぞ」と呼びつける(1枚目の写真、矢印は封筒)。会った時に渡さなかったのは、パコと引き離してパブロと話すためだ〔この男の常套手段〕。パブロが来ると、郵便屋は、「おい、お前、どこかであいつ見たことあるか?」と訊く。パブロは否定。「どのくらい一緒にいた?」。「ほんの少し」。「あいつ、どこから来たか話したか? 話してないか?」(2枚目の写真)「今すぐ家に帰れ。あいつと一緒にいるんじゃない」。実にお節介で、嫌なタイプだ。パコは、パブロが戻ってくると、「次は、どうする? 道を教えてくれるか? タクシーを呼ぶべきか?」と訊く。「道って?」。「村まで。ガレージを見つけないと」。パブロは、親切に村まで歩いて連れて行く。


パブロは、最短コースを取るので、草むらの中も歩くし、きれいなお花畑の近くも通る(1枚目の写真)。「君はパブロだったな。私はフランシスコだ」。「だよね」。「何で『だよね』なんだ?」〔さっき、エンジンのキーを回すため車に乗ったとき、助手席に置いてあった封筒の宛先が「Ciudad Real(シウダード・レアル)に住むフランシスコ(Francisco)何某」だった〕。車道に出てしばらくすると、正面に村が見えてくる。ビジャルエンガ・デル・ロサリオ〔Villaluenga del Rosario〕だ。近くにラ・シエラ・デ・グラサレマ〔la Sierra de Grazalema〕自然公園がある。ともに、映画のロケが行われた場所〔国際空港のあるマラガの西約90キロ〕。村の中の雰囲気は、「誰でもお知り合い」といった感じ。だから、余所者を連れたパブロは非常に目立つ。さっそく、「あれ誰なんだろう?」。パブロのことをよく知らない子が、「父さんじゃないの?」と言い、「お前バカか?」と こき下ろされる〔パブロの父は死んでいる〕。女性が、「可哀相に、あんなことがあれば、あんな風になるのも仕方ないわね」と同情するのは、パブロがうつむいて歩いているからか、村の子供たちと遊ぼうとしないからか?


パブロは、パコをガレージに連れて行く(1枚目の写真)。「前に点検したのはいつだね?」。「1年前かな」。「オイルは交換した?」。「機械のことは弱いんだ」。そのやり取りを、ガレージ屋の息子がじっと見つめている(2枚目の写真)。自分が無視されたように感じたパブロは、近くで赤ん坊にお乳をやっている女性を横目で覗う。乳房がクローズアップされるので、性への目覚めを意味するのか?


場面は、故障した車に移行。ガレージ屋がボンネットを開けて中を調べている。パブロも一緒に付き合っている。ガレージ屋の意見は、車の具合はかなり悪いので、数日預かって検査が必要だというもの。「じゃあ、ここで数日過せってことか? 村にホテルは?」。「ホテルはないが、村の中心にバル〔飲食店〕がある」。「そこに部屋が?」。「ああ、悪くない」。「じゃあ、見てみよう。だが、その前に まず友だちを見つけ出したい。パブロ・ベニテって名前だ。一緒に軍にいた」。「何かの冗談じゃないよな?」。「違う。私たちは何年も会っていない。この辺りに住んでるって話だった。この村かどうかは分からんが」。「情報をくれるとしたら、そのパブロだな」。その時、ようやくパコは、パブロが親友の息子だと気付く。「何だ! 君が、パブロ・ベニテの息子なのか?」(1枚目の写真)。「何年も彼を捜してたのに、偶然その息子に会ってたとは… 驚きだな。父さんは元気か?」。パブロは、答えにくいので、「うん」と言う。事情を知っているガレージ屋は、いづらくなり、後でレッカー車で取りに来ると告げて村に帰って行く。「パブロ・ベニテの息子か。素晴らしい。じゃあ、案内してくれ」。パブロは家に向かわず、再び、お花畑を通って村に向かう(2枚目の写真)。「この辺にいるって知ってたが、村の名前が思い出せなくてな。彼はどうしてる? 自分の店を持ちたいって、いつも言ってた。君は彼に似てるな。とてもハンサムだ」。


パブロが連れて行った先は墓地。パブロは壁の墓碑(?)を、黙ってパコに見せる(1枚目の写真)。パコは友人の死を知って涙を流し、パブロを思い切り抱きしめる(2枚目の写真)。抱擁から解放された後も、パコの嘆き悲しむ様を見て、パブロは驚くとともに、感動したのかもしれない。何れにせよ、お互いの関係が、以前と比べ親密になったことは間違いない。パコにとって、パブロは親友の忘れ形見だし、パブロにとってパコは父のことを想ってくれる優しいオジさんだ。


墓地の前の低い煉瓦塀に座った2人。パコは、「何が起きたんだ?」と訊く。「落ちたんだ」。「どんな風に?」。パブロはうなだれる(1枚目の写真)。それは、パブロにとって最も話したくないことだったので、「病院に3週間いた」と話をはぐらかす。「仲は良かったのか?」。すると、過去の記憶が一瞬甦り、楽しそうな2人が映る。仲は良かったのだ〔それとも、それは、ごくたまの一瞬だったのか?〕。すぐに現在に戻る。パコ:「私たちは、本当に仲が良かった。軍隊ってトコは、良い友達を生むって言うだろ。だが、君の父さんと私は特別だった」。「どんな風に?」。「田舎で行われる軍事演習の時、いつも同じテントだった。彼は笑うのが好きだったが、真面目になると規律一本槍になるんだ」。「もっと話してよ」。「ずい分昔の話だからな。軍務が終わると、連絡が途絶えた。どうしてかな…」。「父さんは凄いんだ。僕に銃の撃ち方を教えてくれた」〔パブロは射撃が巧い〕「ある時、真冬だったけど、僕、雛の暖房用の電球を点け忘れちゃって、朝起きたらみんな死んでた。僕って散漫なトコがあるから」。「許してくれたんだろ?」。「うん」。この言葉とともに、また思い出が甦る。今度は長い。パブロは、父の怒鳴り声に呼ばれて小屋に行くと、雛鳥を入れた箱の中を見せられ、1羽の死んだ雛を渡される(2枚目の写真、矢印は巣箱)。「そこに座れ。羽をむしるんだ。全部だぞ」。パブロがむしり終えた頃、父はピローケースを持って来る。そして、そこに羽を入れさせ、「それで寝ろ」と命じる〔あまり優しい父親とは言えない〕。「お陰で、僕も少しは責任のある人になれた」。「死人のことは、悪く言わないだろ。君は、彼の別の面も知ってるんじゃないか? 時々キレただろ?」。「ううん。父さんはいい人だった」。「極端に走る時があった」。「そんなことないよ!」。「我々には、みんな秘密がある。人間は、不快な体験をすると牡蠣のように閉じ籠もる。誰もが内に真珠を秘めているのに、明かそうとしない。君は、どうなんだ?」。そう訊くと、パコは、パブロの膝に手を置く(3枚目の写真、矢印)。パブロは、父の死の瞬間を断片的に思い出す。その時、老婆に見られていると知ったパコは、膝に置いた手を急いで引っ込める。



パコとパブロは、村の中心にあるバルに行く。パコ:「邪魔しちゃ悪いが、ここに来れば部屋が借りられるって聞いたんで」。女将:「そうですよ」。「空いてるかね?」。「お一人?」。「ああ、私だけだ」。「何日くらいです?」。「取り敢えず今夜。ただの通りがかりなんで」。「いいですよ。何泊かは分からないんですね?」(1枚目の写真)。「車が壊れたんだ。今、ガレージ屋が直してる」。「村には、ご存知の方でも?」。「この辺りじゃ、誰も知らない」。すごく親切そうに見える女将だが、後で、郵便屋と並ぶ性悪女だと分かる。部屋を見に行った2人は、降りてきて、発泡性飲料を注文する。2人はテーブルに座り、パコは、「あれだけ歩いたから、喉が渇いたろ?」と訊く。さらに、「ガールフレンドはいるか?」とも。「僕に? いないよ」。「あの女の子、君を見てるぞ」。「フリアだよ」。「友達かい?」。頷く。「仲のいい友達、それとも、ただの友達?」。「知らない。他に同じ年頃の子、誰もいないから。あの子、両親がいない。死んじゃったんだ」。ここで、女将がドリンクを2本持って来て、栓を抜いて渡す。2人ともグラスに注ぐ(2枚目の写真)。「お祖父ちゃんと住んでる。だけど、頭が変なんだ。野原の土を食べちゃう」。そこに、郵便屋が顔を出す。如何にも親しげにパコと握手した後、テーブルに座り込むと、車がどうなったか尋ねる。ガレージ屋に預けていると答えると、「それはいいね。あの車何年使った?」と訊く。「4・5年かな、たぶん」。「4・5年で、あんな風になるのか?」。「ずい分、走ったからな。それにメカには弱いんだ」。「ちょっと変だが、あんたが そう言うんなら…」。そう言うと、郵便屋は、ワザと帽子をテーブルの上に「忘れて」席を立つ。そして、カウンターにいるフリアの隣に座る。フリアは、ソーシャル・サービスに孤児として連れてかれないための「助っ人」としか見ていないが、郵便屋には別の汚い魂胆がある。その目的のため、明日、家に行くと告げてOKを取る。


郵便屋は、そのまま出て行ってしまう。パブロは、帽子が置いたままになっているのに気付き、「僕、渡してくるよ」と言い、すぐに席を立つ。外で待っていた郵便屋は、「こんなトコで何してる?」と訊く。「パコと一緒だよ」(1枚目の写真)。「見りゃ分かる。さっき言ったじゃないか。奴はお前をダマしてるんだぞ。今だって、あの車は奴ので、5年乗ってると嘘ついた。だが、車は借り物で2年しか使っちゃいない。嘘つくなんて、変だと思わんか? 奴には気をつけろ。今すぐ家に帰るんだ」。テーブルに戻ったパブロに、パコは、「あいつは、帽子をワザと忘れていった。私のことで何か言われたんじゃないのか?」と訊く。「ううん」。「ホントに言わなかった? パブロ、話してごらん」。「車が… 借り物だって」。「その通り。あれは借り物だ。私は、いつも、友達から同じ車を借りてるから、自分の車みたいに思ってる。なあパブロ。私に息子があったら、君と同じくらい好きになるだろうな」。こう言われて、パブロの頬が緩む(2枚目の写真)。2人は外に出て行く。女将は、早速フリアに、「あの男、絶対、見たことあるわ。不快な感じがつきまとってる」と悪口を囁く。


その夜、帰宅したパブロに、母は、「今日は、何してたんだい?」と ぶっきらぼうに尋ねる。「何も」。「どこに行ってた?」。「野原」(1枚目の写真)。「誰と?」。「誰とも」。「誰とも?」。パブロは頷く。「じゃあ、犬を轢きそうになった車はどうなの?」。パブロは思わずドキリとする。母:「郵便屋が話したんだよ」。パブロは、郵便屋の「陰口叩き」ぶりに愛想がつきる(2枚目の写真)。母は、「お前のことが、とっても心配なの」と言いながら、パブロの大嫌いな牛乳を並々と注ぐ。「砂糖入れる?」。「牛乳なんか要らない」。この母親には、息子に対する愛情があるのだろうかと疑ってしまう。


翌朝、パブロは起きると、ベッドの上の写真立てに気付く。そこには父の写真が入れてあった。これをパコに見せて喜ばせてやろう… そう思ったパブロは、写真立てから写真を取り出す(1枚目の写真、矢印)。そして、鏡の前に立つと(2枚目の写真)、自分の顔をつくづく眺め、髪をきれいにとかし、一張羅の純白のシャツを着て出かける。その時、脚本の遊び心で面白いのは、「オズボーンの雄牛」の巨大看板が、白いシャツに因んでホルスタインのようになっていること。パブロが森の中に張ってある紐と戯れるシーンは、DVDのコメンタリーで、監督は「画面に流れるギターの音に合わせた」と言っていた。そう思って観ると、確かに、1本の白い紐しかない時は、1弦を弾く音だけだ。赤い紐が追加されると2弦になり、多色のシーンでは多弦に増える。だから、この紐のシーンは、音楽を画像で表現しているだけで、具体的な意味はない。結構長い紐のシーンが終わると、パブロは真っ赤なお花畑の中を駆け抜ける(3枚目の写真)。



パコは、バルで朝食を食べている。皿を片付けながら、女将が、「あなたの顔って、見れば見るほど、どこかで見たような…」と言い出す。「そうかな? ここに来たのは初めてだが…」。「いいえ、ここじゃない。どこか他で… あなたの顔… 絶対、どこか他の場所で見てるわ」。「ありそうもないな。たぶん、他の誰かと混同してるんだろう」。「いいえ、あなたのような顔は一度見たら忘れないもの。ところで、ここには長くご滞在?」。「前にも言ったが、分からない。ガレージ屋次第だ」。「まだ直らないんです?」。「これから見に行く」(1枚目の写真)。カウンターに戻った女将は、自分の息子に、「あの男、刑務所にいたのよ。今、確信できた。ヘレスで見たのよ。私が知ってるとも 知らないで」と小声で嬉しそうに言う。この「噂」は、郵便屋を通じて村中に広まる。他人の「隠したいと思う過去」を、ペラペラしゃべるのは、本当に嫌な性格だ。ガレージ屋が車の状況を何と説明したのかは分からない。映るのは、パコが、ガレージ屋の息子と仲良く話す姿。そこに、やってきたパブロは、「仲の良さそうな雰囲気」に嫉妬し、近づけない(2枚目の写真、矢印はパブロ)。せっかくおめかしして写真まで持って来てあげたのに、と残念そうに引き返す。途中でフリアがパブロの前に現われ、「どこ行くの? 真っ白な きれいなおべべ着て、そのご立派な七三分けの髪は何よ?」と皮肉る。「散歩だよ」(3枚目の写真)。「へーえ、そう? あの男と、いつも一緒だものね。そうか… あんたみたいに可愛い子なら、あの男も首ったけってことか」。「バカ言うなよ、フリア。もう行くから」。「ねえ、後で隠れ家で会わない?」。「いいよ、いつ?」。「後で。ちょっとしたプレゼントあげる」。



フリアに言われた「首ったけ」に気をよくしたパブロは、もう一度村に引き返す。今度戻った時は、パコは1人きりだった。パブロに会ったパコは、パブロの頬を触ったり、肩を抱いたり、髪の毛をもじゃもじゃにしたりして可愛がる。パコにはホモの気は一切ない。ただ、親友の息子が可愛くて仕方がないのだ。一方のパブロには、父の代わりの存在として、今まで味わったことない感情をパコに対して抱いている。それは、まだ未分化な思春期の少年にとって、ホモに分類されるようなものかもしれないが、パブロは愛情に飢えている。母は投げやりで、フリアは年上で子供扱いしかしてくれない。そんな中でパコは自分を必要としてくれている。そこで、パブロは、自分が一番大切にしていたものを差し出す。父の写真だ。それを手にしたパコは、パブロの心遣いが嬉しく、思わず、髪の毛にキスする(1枚目の写真、矢印は写真)。パブロにとっても、パコの喜びと、自分に対する「愛」は、心をうっとりさせてくれるご褒美だった。パブロとパコは、そのまま村を出て、丘に向かう(2枚目の写真)。そこで、パブロは自慢げに「詩を知ってるよ」と言い、「暗唱してごらん」と言われる。そこで、パブロがうろ覚えで間違えながら訥々(とつとつ)と口にするのは、チリの詩人パブロ・ネルーダ(1904-73)が20歳の時に書いた『二〇の愛の詩と一つの絶望の歌〔Veinte poemas de amor y una canción desesperada〕』の15番の冒頭の部分。田村さと子訳編、思潮社、海外詩文庫14の訳によれば、「黙っているときのおまえが好きだ うつろなようすで〔Me gustas cuando callas porque estás como ausente〕。遠くで おれに耳を傾けているのに おれの声はおまえに届かない〔y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca〕。おまえの目はどこかに飛び去ってしまったかのようだ〔Parece que los ojos se te hubieran volado〕」の部分。あまりの下手さに、パコは「なんだ、メチャメチャじゃないか」と呆れる。パブロ:「僕の頭脳はコンピュータなんだけど、今、壊れてるんだ」。


丘の上の木の下で。パコは、パブロの行動を見ていて、父との間に何か確執があったのではないかと考え、解放してやろうと考える。そこで、ゲームをしようと言い出し、地面に横にならせる。「目を閉じて。気を楽に。私を信じるんだ、いいね? 君の体は、ゆっくりと地面の中に沈んでいく。どんどん沈んで暗闇となる。小さな光が見える…」(1枚目の写真)「1人の少年がいる。怖いけど、どんどん近づいていく。よく見ると、それは、君の知っている子だった…」。こうした催眠術のような言葉を背景として、パブロが封印してきた事故の映像が再現される。父は、屋根に登って瓦を修理していた。しかし、完全には屋根に登らず、足は、立てかけた梯子の上に乗っている。そこに、遊びから帰ったパブロがやってきて、何も考えずに梯子を外してしまう(2枚目の写真)。父の足は梯子の最上段に乗っていたので、パブロには見えなかったのだ。父は、屋根から落ち、頭を強く打ってひどく出血し、意識不明になる。


パコの言葉は続く。「それは君自身だった。その子は 立ち上がり、近づくと、腕を伸ばし、君をぎゅっと抱きしめる。この抱擁は、君がどんな人間で、何をすべきなのかを分からせてくれる。君はいい子だ。ずっとそうだった。たとえ、過去に過ちを犯したとしても、それは罪には当たらない。他人が何を言おうが関係ない。大事なのは君だけ。そして、君はいい子だ」。パブロはゆっくりと目を開く。今まで、心の中に封じ込め、忘れ去ろうとしてきた人生最悪の瞬間を再体験し、それに対する赦しの癒しを与えられたのだ。パコは、パブロにとって、ただの父の親友ではなく、過去のしがらみから解放してくれた恩人となる。パブロは、感謝を込めてパコを見つめる。その視線に耐えられなったパコが立ち上がると、パブロは思わずパコを抱きしめる(2枚目の写真)。そのあと、パブロは、フリアとの約束を守ろうと、走って家に戻る。パープルのお花畑が美しい(3枚目の写真)。一瞬、白い風船が並ぶ風景が映るが、それは、パブロの高揚した心を表徴しているのだろう。



隠れ家では、フリアがイライラして待っている。それでも待ち続けるとは、よほど暇なのか? パブロに想いがあるのか? パブロは、家から持ち出した銃を持って、ようやく現れる。フリアにとって、銃などどうでもいいのだが、パブロは上手なところを見せたくてたまらない。「またなの?」。「見てて」。そして、10数メートル離れたガラス瓶に、外れることなく何回も命中させる。いい加減うんざりしたフリアは、「もう十分でしょ」と 銃を取り上げる。そして、パブロと向かい合って床に座ると、最近のパブロを非難し〔パコにかまけて、フリアを見ようともしない〕、「ちっとも会えないから、退屈でつまんない」と前置きした後で、パブロが9歳にしか見えないと侮る。当然、パブロは13歳だと反論し、フリアの次の言葉を引き出す。「あんたが13で、女の子に一度もキスしたことがないなら…」。「何だよ?」。「してみたい?」。パブロは、「別に…」と、もじもじ。「何よそれ、死人みたいじゃないの、少しはにっこりしたら?」。「死人じゃないよ」。「なら、証明して」。「どうやって」。「キスして」。パブロは、恐る恐るフリアの頬にキスする。「それがキス? いいことパブロ。もっとちゃんとキスするの」。パブロは、もう一度同じようにする。「これじゃあ、教えてあげないとね。教えて欲しい?」。「さあ」。フリアは頬に強くキスし、「これは手始め。覚悟なさい」と言って、キスを始める。ここで、カメラは2人から逸れ、外の景色を写す。言葉だけが聞こえる。フリア:「あんたの番よ」「気に入ったみたいね」。パブロ:「そこ、下げるの?」。カメラが元に戻ると、パブロは慌てて逃げて行くところ。この間に何があったのかは、少し後でパブロが思い出すので、よく分かる。パブロは、嫌々キスさせられ(2枚目の写真)、フリアはパブロのズボンを下げてしまう(3枚目の写真)。パブロにとっては、怖い以外の何ものでもなかった。



一方、フリアの家の外では、郵便屋がイライラしながら待っていた。郵便屋を家に入れたフリアは、ソーシャル・サービスがどうなるかということしか念頭にない。しかし、郵便屋は、指でフリアの膝を触り、イスをフリアにくっつける。フリアがイスを離すと、またくっつける。そして、手を股まで伸ばし(1枚目の写真)、さらに、首筋にキスし、肩を抱き、「好きだよ」と囁くと、ベッドに連れ込む。こうしたことを、白昼堂々、認知症とはいえ祖父の見ている目の前でやる。この男、厚かましい性格で、いい加減な噂をバラまくだけでなく、15歳の少女に対する性的虐待まで… これほど許せない「映画の登場人物」も珍しい。夕方、フリアの家から出てきたところを偶然パコに見られた郵便屋は、「遅くまで大変だな。バッグは忘れたのか?」と言われ、恥ずかしくて顔向けできない。そして、夜。ベッドに仰向けに寝たパブロの頭の中には、いろいろなシーンが甦る。ガレージで授乳させていた女性の乳房、隠れ家の中での先ほど紹介した映像…。パブロの手が下に伸び(2枚目の写真)、オナニーが始まる。その先の画像のほとんどは相手がフリアだが、中に、パコが膝に手を置いた時のものも入っている。これは、パブロの二面性を示そうとしているのかも。翌朝、フリアに会いに行ったパブロは、パコのことを、「今までで、サイコーの友だちだ」と言い、「家に来て、一緒に住んでくれたら、父さんみたいになれる」とも言う。フリアは、全く関心を示さない。しばらく考えたパブロは(3枚目の写真)、「フリア、昨日のことだけど… もし、よければ、その… 舐めてもいいよ」と勇気を出して口にする。昨夜、郵便屋と初体験したフリアは、パコのような子供など、もうどうでもいい。そこで、「もういい」と邪険に言うと、「じゃあね」と出て行ってしまう。「彼にやってもらったら?」。

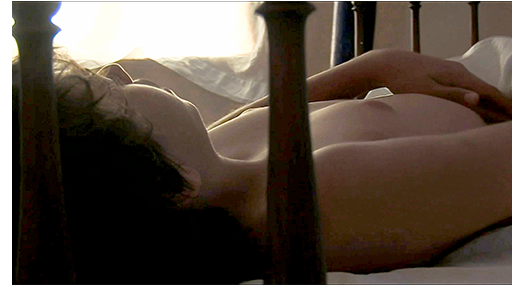

寂しくなったパブロは、村まで出向いてパコと会うと、湖に連れて行く。「気に入った?」。「いいトコだな。ここが、君の好きな場所なのか?」。「そうだよ」。パコが倒木に腰を降ろすと、パブロは水際まで歩いて行く(1枚目の写真)。この湖の撮影場所は、グアダルカシン貯水池。ダムで堰き止められた人工の湖なので、水の中に木が生えている。パブロにとって、ここがなぜ「好きな場所」なのかは、よく分からない。ここで、また過去の記憶が甦る。野原に、鶏の死骸が2羽。それを見た父は、「これで、あの犬とはお別れだ」と怒鳴りながら、寝ているパブロをベッドから引きずり出す。「さっさと、服を着て 外に出ろ!」。パブロが急いで外に出て行くと、父は、犬の首を縛ったロープと、大きな石を手にしている。「このロープと石を持って、すべきことをやって来い」。「お願い、もう一度チャンスを与えて」。「処分するまで戻ってくるな」。父は、パブロが何と言って頼んでも耳を貸してくれない(2枚目の写真、矢印は1匹目の愛犬、2匹目はパコに轢かれそうになった)〔この父親は、想像以上にパブロに厳しい〕。パブロは、犬を殺さないで済むよう、石を投げつけて追い払おうとするが、何をしても逃げてくれない。そこで、パブロは仕方なく湖まで連れて行き、犬に泣いて別れを告げた後、ロープに石を結びつける。そして、石を手に持ち、犬を湖に引っ張り入れる(3枚目の写真、矢印は石)。最後は、犬を抱いて中に入って行き、石を離す。犬は溺れて死ね。その「入水」した場所が、1枚目の写真でパブロが立っている所。だから、もう一度、問いかけたい。パブロにとって、ここがなぜ「好きな場所」なのだろう?



パブロは、しばらく水面を見ていると、パコを振り向き、「泳がない?」と誘う。「今? ここで? やめとくよ」。「僕、泳ぐよ」。パブロが、オレンジのシャツを脱いだのを見たパコは、「シャツを着たまま泳いだ方がいい。それ、3日も着てるぞ」とアドバイス。しかし、パブロは、水泳パンツだけになって、「ねえ、泳ごうよ」と再度誘う。「こんなトコで泳いで、怖くないのか?」〔人工の湖なので、急に深くなる〕。パブロは、1人で飛び込む。パブロが水と戯れるシーンがしばらく続く。満喫したパブロは湖から出る(1枚目の写真)。太陽の光が水面に反射して美しい。パブロは、「魚って、なぜこんなことするか知ってる?」と、口をパクパクさせる。「さあ」。「鼻を食べるんだ」。「魚に鼻なんかないぞ」。「もちろん。もう食べちゃったからね」。パブロは、このジョークを笑顔で言うが、パコは何となく元気がない(2枚目の写真)。それを見たパブロは決心する(3枚目の写真)。



そして、その場で、水泳パンツを脱ぎ、手で絞る(1枚目の写真、矢印は黒い水泳パンツ)。そして、脱ぎ捨ててあった服を取りに行くと、パコの前に、身を捧げるように座り込む(2枚目の写真)。この時のパブロの心境は理解し難い。少なくとも、パブロは、「大人の前で少年が全裸になることの社会的問題性」を認識していなかった。だから、常識的なパコは、すぐに、「それじゃ寒いぞ。着た方がいい。こんなトコ 見られたら、何て言われるか」と、穏やかに止めさせる。パルコは、自分の決死の好意が、「見られたら、何て言われるか」という世間体によって拒絶されたことに傷つく(3枚目の写真)。



そこに、あの「うざったい」郵便屋が現れる。こんな場所に配達先があるとは思えないので、恐らく、パブロと一緒に出かけるのを見て 後をつけてきたのだろう。幸い、パブロが全裸でなくてよかった〔パコは予想していた〕。郵便屋は、「また、あんたか」と如何にも驚いたように言う。「バカンスの奴らかと思ったよ。ここは、ピクニックで人気があるからな。ところで、ガレージ屋からの伝言だ。車は直ったそうだ。だから、急いでるなら、いつでも出て行けるぞ」。「そうか、えらく遅かったな?」。「ガレージ屋がか?」。「あんただよ。私を見つけるのに手間取ったな」。「俺が? まさか」。「下手な芝居は止めろ!」。「違うって。ここは通常の配達ルートだ」。しかし、ズバリ言われてしまったので、話し相手を変えようとする。「とにかくだ、俺は、パブロに言いたいことがある」。そう言うと、何度も、「パブロ」と呼びかけるが、パブロはそっぽを向いて郵便屋を見ようともしない(1枚目の写真)。「じゃあ、あんたが言ってやれよ。今まで隠して言わなかったことを。2年間、セビーリャの刑務所に入ってたんだろ」。「そんな噂が立ってるのか? バルの女将が、ヘレスで私を見たと言ったんだろ?」。「だが、それだけじゃない、女将がヘレスで見たのは、あんたが『誰かさん』〔パブロの母〕と一緒のトコなのさ」。この言葉にカッときたパコは、すくっと立ち上がると、「そろそろ、消えてもらう時がきたようだ。お前には、ほとほとうんざりした」と詰めより、帽子を投げ捨て、「失せろ!」と命じる。口だけ達者の好色男は、コソコソと逃げ出す。恐らく、他のところでさんざ悪口を吹聴するのだろう。クズが去ると、パコは、「刑務所に入ってたと聞いてショックだったか?」と尋ねる。「ううん」。「2年、ムショに入ってた」(2枚目の写真)。「どうして?」。「たまたま、盗品を売ってしまった。それと知らずにな。信じるか?」。「うん」。「そろそろ、出て行く時がきたようだ」。「そんな、ダメだよ。村にいてよ」。「だがな、噂が立ってる」。「家に来てよ」。「母さんが大喜びするぞ」。「母さん? あなたは僕の友だちだよ」。「そうだな」。「でも、どうして行っちゃうの? 分かんないよ」(3枚目の写真)。しかし、郵便屋と女将がいるような、こんな小さな村では、『人の噂も七十五日』では済まないことをパコはよく承知していた。そこで、「さあ、行こう」と会話を打ち切る。



2人が湖岸から村に向かう道を歩いていると、反対側から湖に泳ぎにきた村の子供3人と出会う(1枚目の写真)。しばらく歩き、村への分岐点までまで来た時、パコは、「ちょっと考えることがある。数時間したら 村の広場で会おう」と提案する。「しばらくフリアと会ってきたらどうだ? そしたら、あとでウブリケ〔村の西南西6キロにある別の村〕まで連れてってやろう」(2枚目の写真)。別れると、パコは急ぎ足でどこかに向かう〔向かった先は、パブロの家〕。


一方、湖では、3人がパンツだけになって泳いでいる。最初は仲良く泳いでいたが、一旦岸にあがった後、ガレージ屋の息子が2人から石を投げられたり、パンツを下げるなどの嫌がらせを受ける(1枚目の写真)。そこで、1人で湖に入ると、水の中から生えている大木によじ登る(2枚目の写真)。岸に残った2人のうちの1人は、ガレージ屋の息子に向かって石〔小石ではなく、なかり大きい〕を投げつける。そして、その石が顔面を直撃し、彼は木から落ちる。水に落ちたまま、浮かんでいる姿を見た、もう1人は、湖に飛び込んで調べに行く(3枚目の写真)。ガレージ屋の息子が死んでいるのが分かると、その子は大急ぎで戻って来て、石を投げた子を「何てことしたんだ!」と突き飛ばし、「あいつの父さんを呼びに行く」と脱いだ服を拾い始める、その後の言葉は、どちらが話しているのか区別がつかない。「何も起きなかった。いいな?」「一言も話すな。俺たちは何もしてない」「黙ってると誓え!」。2人は、死体を放置したまま、村に走っていく。



しばらくして、村からガレージ屋に加え、郵便屋たちが駆けつける。父親であるガレージ屋は、水面に浮かんでいる息子の遺体を抱き上げると、助っ人に渡す(1枚目の写真)。父親は、知らせに来た2人を咎めるように見るが、2人は、「知らないよ」「あっちで遊んでたから」「誰もいなかった」(2枚目の写真)「北から来たあの男だけだよ」。この最後の、パコに罪をなすりつける言葉を敢えて口にしたのは、石をぶつけた方の悪ガキ。性根が腐っている。郵便屋は、すぐに、「車の持ち主だ!」とガレージ屋に教える。ガレージ屋と郵便屋は、復讐のため村に向かう。


パブロは、村には向かわず、銃の練習をしようと、銃を取りに家に戻る。そして、銃を持ってドアから出ようとした時、ドアの脇の帽子掛けに、パコの帽子が掛けてあるのに気付く(1枚目の写真、矢印はパコのパナマ帽)。パブロは、まさかと思いつつ母の寝室を覗くと、ベッドの上では母とパコがセックスを終えたところ。パコは、ヘッドボードに上半身をもたせかけ、母はパコの胸に頭を乗せている。「暑いわね」。「ここに引っ越したのは、君の考えだろ」。「パコ、こんなの上手くいかない」。「村人のせいでか?」。「そうよ」。「あのクソどもめ。君の息子とは楽勝だったのに。君は難しいって言ってたが、2日もたたないのに、ここで一緒に住もうと招いてくれたぞ」。そして、「バルの女に、ヘレスで君と一緒のトコを見られた」と話す。「まさか! ローラが?」。「ああ」。「いつかしら?」。「さあな」。「一番腹立たしいのは、郵便屋のクソだ。君の旦那より悪い。冥福は祈るがな。最悪の2人ってトコかな。だが、息子の方とは、うまくいってる。パブロって、ちょっと変わってないか?」。「『変わって』って?」。「ちょっと普通でないというか…」。ここでパコが思わず笑ってしまう(2枚目の写真)。自分の誠意を笑われたと思い、カッときたパブロは、「ろくでなし!」と叫んでドアを開ける。2人は不意を突かれて大慌て。パブロは、そのまま、「この嘘つき! なんで、ここに来たんだ?!」と怒鳴りながら、外に出て行く。



パブロが銃に弾を込め、タオルを巻いただけで外に出て来たパコに向けると、銃の奪い合いになる。そこに、一番に駆けつけたのが、あの、どうしようもなくお節介で役立たずで好色の郵便屋〔なぜ、ここに来たのだろうか? 一旦、村に行き、そこにいなかったから来たのだろうか? それにしてもなぜ? パブロはパコを一度も家に連れて来ていないのに…〕。郵便屋を加えた3人で銃を奪い合う(1枚目の写真)。銃をもぎ取った郵便屋はパコを撃ち、パコは地面に倒れて動かない〔郵便屋は、如何にも「やったぜ」という顔だが、死んでいたら殺人罪になるのではないか?〕。そこに、下着姿のパブロの母が出てきて、パブロが死んだと思い、大声で泣き出す。そこに、さらにやって来たのが、嫌な奴No.2の女将。母のことを、「恥知らずのふしだら女!」と罵る。この村には、まともな人間はいないのだろうか? あまりの惨状に、パブロは何度も「パパ」と口にすると、逃げ出す(2枚目の写真、矢印)。この「パパ」は、コメンタリーによれば、天国の父に帰ってきて、この場を何とかして欲しいとする願望だとか。湖の近くまで走っていったパブロは、地面に座りこむと、絶望のあまり泣き崩れる(3枚目の写真)。



映画は、冒頭のシーンに戻る。車椅子らしきものに座ったパコが、20歳前後のパブロに対し、一方的に話しかける。残念ながら、正確な訳は紹介できない。英語、オランダ語、ポルトガル語の字幕を並べてみたが、要点がさっぱり分からない。話の内容は、幾つかに整理できる。最初は、銃撃事件の事後談。「お母さんをあの場所から引き離すのに2年間かかった」と言うので、パブロの母は、あの嫌らしい村のそばに2年もいたことになる。「君は、何も助けになってくれかった」。パルコは、13歳なので一人では暮らせない。母と一緒にいて、しかも、村から離れることを拒んだということだろうか? そして、「君のお母さんが亡くなった時、私は君を捜した」。パブロの母が村を出た時、パブロは15歳。もし、パブロが18歳になってから母が死んだのなら、パブロがどこか他所にいてもおかしくはない。このあと、パコの話は、過去に戻る。「君のお母さんが話したかどうか知らないが、私たちはお互いとても好きだった。私も君のお父さんも、君のお母さんを愛した。2人の友達が同じ女性を愛したんだ。彼女は困ってしまった。そして、君が生まれた。君の父さんの方が一枚上手で 素早かった」。そして、3番目。現在の状況に言及する。「ここに来てもらったのは、どうしても話しておきたかったからなんだ」。この次の言葉が、理解できない。「私は、君をこれっぽっちも咎めていない」。パコに、パブロを咎める権利があるのだろうか? 銃を持っていたこと? しかし、撃ったのは郵便屋だ。母とのセックスを咎めたこと? 咎められて当然で、逆はあり得ない。パブロが母の離村を勧めたり、成人してから母を放っておいたこと? いきなりそう言われても、観客は見ていないのだから、もしそんなことで咎めるとした卑怯な脚本だ。「私は、君をこれっぽっちも咎めていない」という言葉が、パブロ→パコに発せられたとしたら、それは、パブロの感じやすい少年期を破壊した張本人への優しい赦しになるかもしれないが、逆は絶対にあり得ない。これは、ただ単に、パコが非常に自分本位の人間だと、言いたいだけの長丁場なのだろうか? 映画は、バス停に座って考え込むパブロのシーンで終わる(2枚目の写真)。


G の先頭に戻る L の先頭に戻る い の先頭に戻る
スペイン の先頭に戻る 2000年代後半 の先頭に戻る